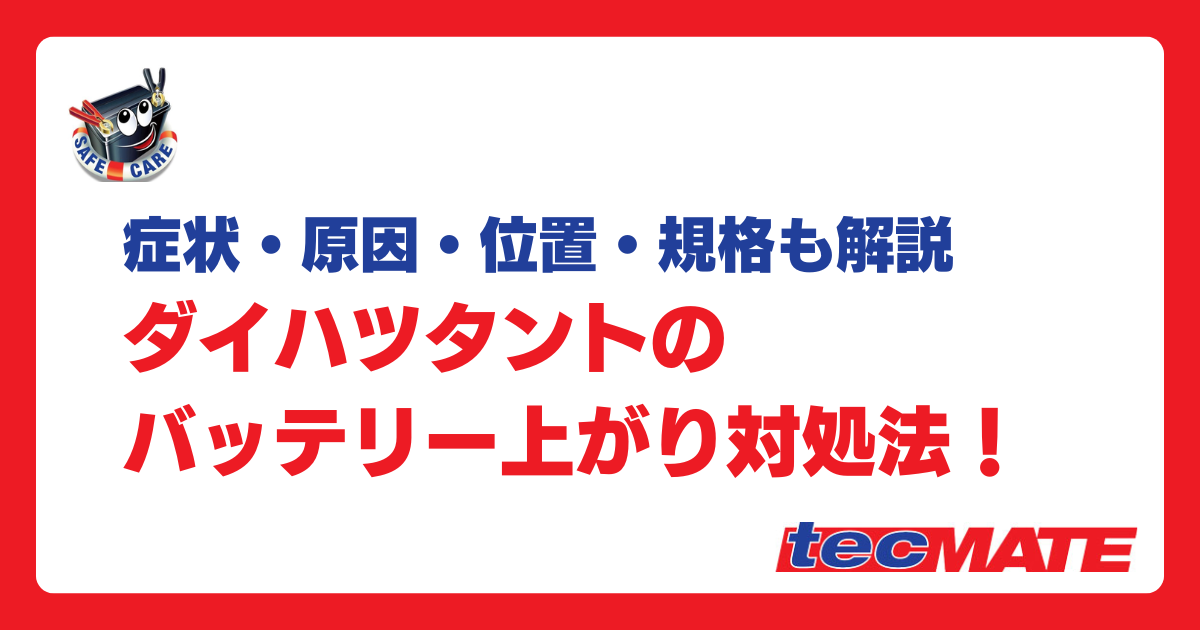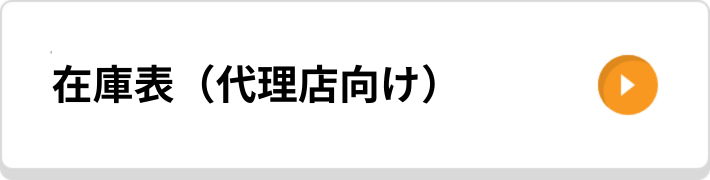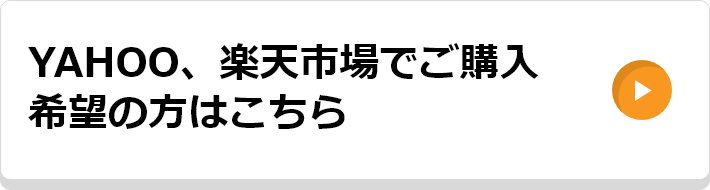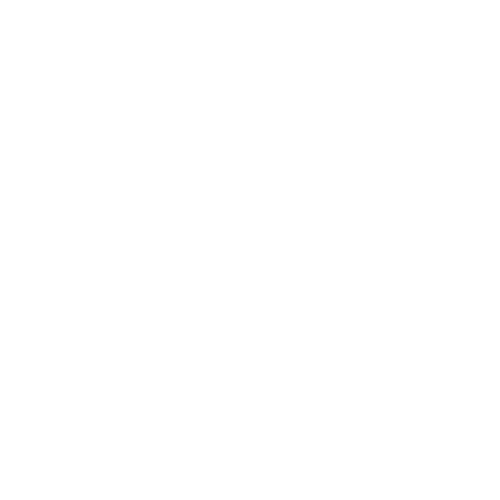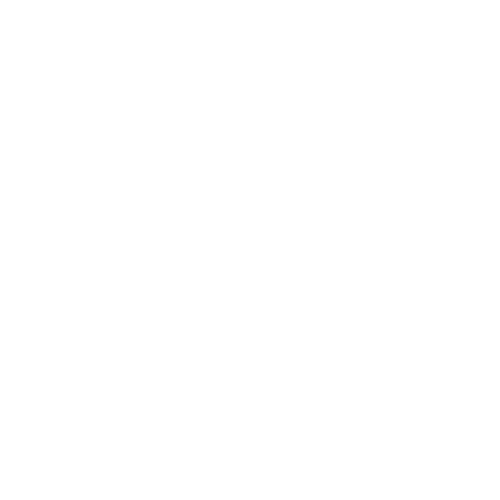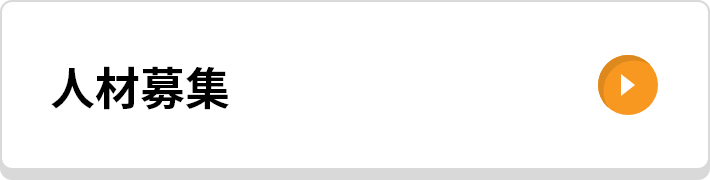「あれ、タントのキーが反応しない…どうしよう?」
「最近エンジンの掛かりが悪いけど、もしかしてバッテリーが弱ってるのかな?」
そんな突然のトラブルに慌てないため、そして安心してお出かけするために大切なのが、タントの「バッテリー上がり」への備えです。
この記事を読めば、バッテリー上がりの原因や対処法がわかります。また、ご自身のタントのバッテリー位置や規格サイズも分かり、突然のトラブルにも落ち着いて対応できるようになります。
大切な愛車のために、バッテリーの知識をしっかり備えておきましょう。
ダイハツタントのバッテリー上がりで現れる主な5つの症状
バッテリーが弱ってくると、車はSOSとして色々なサインを出します。ここでは、バッテリー上がりを疑うべき具体的な症状について、一つずつ確認していきましょう。
- エンジンがかからない
- キーレスが反応しない
- ドアロックが開かない
- メーター内の警告灯マークが点灯・点滅する
- ライトや室内灯が暗い
エンジンがかからない
バッテリーが上がってしまった時、ドライバーが最初に気づく一番分かりやすい症状が「エンジンがかからない」ことです。
音が明らかに弱々しく「キュル、キュル…」と途切れ途切れになったり、さらに電力が減っていると「カチカチ」や「ジジジ」といった機械的な音がするだけで、セルモーターが回らなくなったりします。
エンジンをかける動作は車の中で最も電力を使うため、バッテリー上がりがはっきりと分かるサインといえるでしょう。
キーレスが反応しない
リモコンキー(キーレスエントリー)のボタンを押しても、ドアロックが反応しなくなるのも、バッテリー上がりのよくある症状の一つです。
スマートキーを携帯して車に近づいても、自動でロックが解除されない場合も同様です。
これらの症状は、キーからの電波を受け取る車側のシステムや、ドアロックを動かすモーターの電力が、バッテリーから供給されていないために起こります。
ただし、スマートキー本体の電池切れでも同じような症状が出ることがあります。
キー本体の電池切れなら、内蔵されているメカニカルキー(物理的な鍵)でドアを開ければエンジンはかかることが多いです。一方で、車側のバッテリー上がりだと、ドアを開けた後もエンジンがかからない、室内灯が点かないなど、他の症状も一緒に出ていることが多いです。
バッテリー上がりを疑ったら、エンジンがかかるかどうかを確認してみましょう。
ドアロックが開かない
バッテリーが上がると、キーレスやスマートキーが反応しないため、ドアロックの施錠・開錠が電動では一切できなくなってしまいます。
ドアロックが開かない時は、スマートキー(電子カードキー)に内蔵されている「メカニカルキー(物理的な鍵)」を使って、手動でドアを開ける必要があります。
タントの場合、多くは運転席ドアノブの鍵穴にメカニカルキーを差し込んで回すことで、ドアを開けることができます。
いざという時のために、ご自身のタントでの開け方を取扱説明書で確認しておくと安心です。
メーター内の警告灯マークが点灯・点滅する
キーをONの位置にした時(プッシュスタートボタンを1回押した時)に、メーターパネルの表示がおかしくなるのもバッテリー上がりの特徴です。
電力が足りないため、メーター全体がぼんやりと暗かったり、チカチカと不安定に点滅したりすることがあります。また、普段は点かないはずの警告灯が一斉に点灯したり、逆にキーをONにしてもメーターが真っ暗なまま、何も表示されなかったりすることもあります。
これらの症状は、メーターや車のコンピュータを正常に動かす電力が足りていないサインです。
ライトや室内灯が暗い
バッテリーの電力が弱ってくると、ライト類の明るさにもはっきりと影響が出ます。
例えば、夜間にヘッドライトを点けても「いつもより明らかに暗いな」と感じたり、室内灯が「暗い」「チカチカ点滅する」、あるいは「まったく点灯しない」といった症状です。
ライトを力強く光らせるための電力が、バッテリーに十分残っていないために起こります。
エンジンをかける前に室内灯などの明るさを確認することは、バッテリーの状態を知る簡単な目安にもなります。
【緊急】ダイハツタントのバッテリーが上がった時の対処法4つ
ここでは、エンジンを再びかけるための具体的な緊急対処法を、落ち着いてできる順にご紹介します。
- バッテリー充電器で回復させる
- 救援車とブースターケーブルでつなぐ(ジャンプスタート)
- ジャンプスターターを使用する
- ロードサービスに救援を依頼する
バッテリー充電器で回復させる
もしバッテリー充電器をお持ちの場合は、充電器で回復させるのがおすすめの方法です。
バッテリー充電器の場合は、エンジンをかけるための応急処置ではなく、バッテリー自体に電気をしっかり補充(充電)する方法です。時間はかかりますが、バッテリーへの負担が最も少なく、根本的な解決につながります。
「オプティメイト7セレクト」のような全自動充電器なら、バッテリーにつないでコンセントに差すだけで、診断から充電まで自動で行ってくれるため、安心して任せることができます。
救援車とブースターケーブルでつなぐ(ジャンプスタート)
もし近くに助けてくれる車(救援車)があり、ブースターケーブルという専用のコードをお持ちなら、電気を分けてもらう「ジャンプスタート」という方法でエンジンをかけられる可能性があります。
ただし、この方法はケーブルをつなぐ順番が非常に重要です。
基本的な手順は以下の通りです。
- 救援車のバッテリーのプラス(+)端子と、タントのバッテリーのプラス(+)端子を赤いケーブルでつなぎます。
- 救援車のバッテリーのマイナス(-)端子と、タントのエンジンルーム内にある金属部分(バッテリーから離れた、塗装されていないボルトなど)を黒いケーブルでつなぎます。
- 救援車のエンジンをかけ、回転数を少し上げます。
- タントのエンジンをかけます(かかったら、すぐにケーブルを外さず数分間そのままにします)。
- 外す時は、つないだ時と逆の順番(黒いケーブルから)で外します。
順番を間違えるとショートして火花が散ったり、車のコンピューターが故障したりすることもあるため、慎重に行う必要があります。
ジャンプスターターを使用する
救援車が見つからない場合でも、「ジャンプスターター」という手のひらサイズほどの専用バッテリーがあれば、自分一人でエンジンをかけることができます。
使い方はブースターケーブルと似ていますが、救援車が不要なのが大きな違いです。
ジャンプスターター本体のプラス(+)とマイナス(-)のクリップを、タントのバッテリー端子(または救援端子)と金属部分に正しく接続し、スターターの電源を入れてからエンジンをかけます。
ただし、ジャンプスターターを事前に充電しておく必要があることと、長時間使用しないと自然放電の恐れがある点には注意が必要です。
ロードサービスに救援を依頼する
ご自身で作業するのが不安な時や、道具がない時には、無理をせずプロを呼ぶのが確実な方法です。
代表的なのはJAF(日本自動車連盟)ですが、もし自動車保険(任意保険)に加入されているなら、その保険にロードサービスが付帯している場合がほとんどです。
JAF会員の方なら、バッテリー上がりは基本的に無料で対応してもらえます。
保険付帯のロードサービスも、多くの場合無料で対応してくれますが、利用回数に制限が設けられていることもあるため、一度ご自身の保険証券などを確認しておくと良いでしょう。
電話一本で専門のスタッフが駆けつけてくれるので、特に夜間や悪天候の時には頼りになる存在です。
なぜ?ダイハツタントのバッテリーが上がる5つの主な原因
バッテリー上がりは、単純なミスから車の乗り方、バッテリーの寿命まで様々な原因で起こります。ここでは、タントで特に多い5つの主な原因を見ていきましょう。
- ライト類(ヘッドライト・室内灯)の消し忘れ
- 運転頻度が低い(長期間乗らない)
- 「ちょい乗り」の繰り返しによる充電不足
- バッテリー本体の寿命(一般的に2~3年)
- 電装品(ドラレコなど)による電力消費
ライト類(ヘッドライト・室内灯)の消し忘れ
最も単純で、誰にでも起こり得るのがライト類の消し忘れです。
最近のタントはヘッドライトが自動で消えることが多いですが、室内灯(ルームランプ)やスモールランプ(車幅灯)は手動で消す必要があるかもしれません。
これらが一晩中点いたままだと、バッテリーの電気は空になってしまいます。
車から降りる時には、メーターパネルの警告灯が消えているか、スイッチがOFFになっているかを確認する習慣をつけておくと安心です。
運転頻度が低い(長期間乗らない)
車はエンジンを止めている間も、時計やカーナビのメモリー保持のために、実は少しずつ電気を使っています(暗電流)。
同時に、バッテリー自体も「自然放電」といって電気を失っていきます。
1〜2週間程度なら問題ないことが多いのですが、1ヶ月以上乗らない期間が続くと、消費する電力量が自然に回復する量を上回り、バッテリーが上がってしまいます。
バッテリー充電器で定期的にメンテナンスをするか、長期間乗らずに放置しないようにしましょう。
「ちょい乗り」の繰り返しによる充電不足
バッテリーにとって意外と負担が大きいのが、片道10分程度の「ちょい乗り」の繰り返しです。
エンジンをかける瞬間、バッテリーは非常に大きな電力を消費します。そのため、走行時間が短いと、使った分を十分に取り戻せないまま、また次のエンジン始動で電気を使ってしまいます。
この「消費が充電を上回る」状態が続くと、バッテリー残量はどんどん減り、ある日突然エンジンがかからなくなってしまいます。
バッテリー本体の寿命(一般的に2~3年)
車のバッテリーはスマートフォンのバッテリーと同じ消耗品で、いつかは寿命を迎えます。
一般的な交換の目安は2〜3年と言われています。
特にアイドリングストップ機能が付いている車は、信号待ちなどでエンジンの停止・再始動を繰り返すため、バッテリーへの負荷が大きくなりがちです。
そのため、高性能な専用バッテリーが使われていますが、従来の車よりも寿命が短くなる傾向があることも知っておくと良いでしょう。
3年以上交換していない場合は、特に症状が出ていなくても点検してもらうことをおすすめします。
電装品(ドラレコなど)による電力消費
ドライブレコーダーや後付けのセキュリティ機器が、バッテリー上がりの原因になることもあります。
特に、エンジン停止中も作動する「駐車監視機能」は、設定によっては待機中も電気を消費し続けます。
バッテリーの状態に対して電装品の消費電力が大きいと、数日車に乗らなかっただけでバッテリーが上がってしまうケースも少なくありません。
電装品を取り付ける際は、バッテリーの電圧が一定以下になると自動で停止する機能が付いた製品を選ぶと安心です。
ダイハツタントのバッテリー上がりを防ぐ根本的な予防策とは?
バッテリー上がりは、日頃の少しの心がけとメンテナンスで防ぐことができます。ここでは、タントのバッテリーを守るための3つの基本的な予防策を紹介します。
- バッテリー充電器で定期的にフル充電する
- 定期的に30分以上運転する
- バッテリーの寿命(2~3年)を目安に点検・交換する
バッテリー充電器で定期的にフル充電する
おすすめの予防策は「バッテリー充電器」を使った定期的なメンテナンスです。
車の走行による充電だけでは、バッテリーを100%の満充電状態に保つのはなかなか難しいです。
乗らない時間を使って、家庭用のコンセントからバッテリー充電器を接続し、電気をしっかり補充してあげます。定期的にフル充電することは、バッテリー内部の劣化を防ぎ、バッテリー本来の性能を長持ちさせることにもつながります。
バッテリー充電器をお持ちでない方は、ぜひご検討ください。
定期的に30分以上運転する
バッテリーを健康に保つ簡単な方法は、定期的に車を運転することです。
車はエンジンがかかっている間に発電機を回して、バッテリーを充電しています。
エンジン始動時には大きな電気を使いますが、その電気をしっかり回復させるには「1週間に1回、30分以上」の走行が目安とされています。
もし運転頻度が低い場合や、毎回10分程度の「ちょい乗り」が多い場合は、使った電気を充電しきれず、バッテリーが弱りやすくなるので注意が必要です。
バッテリーの寿命(2~3年)を目安に点検・交換する
一般的なバッテリー交換の目安は、使用開始から「2〜3年」と言われています。
特に、近年のタントに多いアイドリングストップ車は、信号待ちなどでエンジンの停止と再始動を繰り返すため、バッテリーへの負担がとても大きいです。
こうした車には高性能な専用バッテリーが使われていますが、その分、従来の車より寿命が短くなる傾向もあります。
3年以上交換していない場合は、突然のトラブルを避けるためにも、車検や点検のタイミングでバッテリーの状態をチェックしてもらうと安心です。
オプティメイトはサルフェーション除去機能付き
オプティメイト(OptiMate 7 Select)は、バッテリーの寿命を縮める原因となるサルフェーションを除去する機能を備えています。サルフェーションとは、バッテリー内部で発生する硫酸鉛結晶のことで、これが電極を覆うことで充電効率が低下し、最終的に寿命短縮に繋がります。
オプティメイトは、このサルフェーションを取り除くために、最大22Vの高電圧※と独自のパルス充電技術を採用しています。バッテリーの状態をリアルタイムで監視しながら、バッテリーの状況に合わせてサルフェーションを除去します。
※車載時には最大16Vでの回復充電です。車両側を保護するために自動で制御をします。
ダイハツタントのバッテリー位置と規格サイズ
バッテリーの点検や交換、充電をご自身で行う場合、搭載位置と適合規格の確認が不可欠です。ここでは、タントのバッテリーに関する基礎知識を解説します。
ダイハツタントのバッテリー搭載位置はどこ?
ダイハツタントのバッテリーは、歴代のモデルを通じて、基本的に「ボンネットの中」に搭載されています。
助手席のシート下や荷室の床下に搭載されているタイプではないため、点検や交換作業は比較的しやすいと言えるでしょう。
ただし、安全に作業するためにも、ご自身の車の正確な搭載位置と、端子を外す順番などは、必ず取扱説明書で確認してください。
ダイハツタントのバッテリー規格・サイズ【一覧表】
バッテリーを交換する際は、必ずタントに適合した「規格(サイズ)」のものを選ぶ必要があります。
以下は、タントの主なモデルと適合規格の代表例です。
| 販売期間 | エンジン型式 | 対応車 | 標準搭載バッテリー | 寒冷地仕様バッテリー |
| 2019/7~2022/10 | 6BA-LA650S | アイドリングストップ車 | M-42 | M-42 |
| 2019/7~ | 5BA-LA650S | アイドリングストップ車 | M-42 | M-42 |
| 2013/10~2019/7 | DBA-LA600S | アイドリングストップ車 | M-42 | M-42 |
| 2011/11~2013/10 | DBA-L375S | アイドリングストップ車 | M-42 | M-42 |
| 2011/6~2011/11 | DBA-L385S | 充電制御車 | 44B20L | 44B20L |
この表はあくまで一例です。同じモデルでも年式やグレード、寒冷地仕様などで適合品が異なる場合があります。
失敗しないためにも、必ず取扱説明書を見て確認するか、バッテリーメーカーの公式サイトで適合検索をしてください。
ダイハツタントのバッテリー上がり対策なら「オプティメイト7セレクト」
バッテリー上がりを未然に防ぎ、タントのバッテリーを良い状態に保つには、高性能なバッテリー充電器の活用がとても効果的です。
もしタント用の充電器を検討しているなら、「オプティメイト7セレクト」が一つの選択肢になるでしょう。
この充電器には、バッテリー管理を自動化する、以下のような機能が備わっています。
| 機能の名称 | 機能の内容 |
| 全自動マルチステップ充電機能 | バッテリーの状態を自動分析し、最適な多段階プログラムで満充電にします。 |
| アンプマティック機能 | バッテリーの状態を自動分析し、最適な多段階プログラムで満充電にします。 |
| 超強力パルス回復充電機能 | 弱ったバッテリー内部のサルフェーションを分解・除去し、性能の回復を助けます。 |
| バッテリー診断機能 | 充電前や充電中もバッテリー状態を監視し、トラブルを未然に防ぎます。 |
| メンテナンス機能 | フル充電後も「つなぎっぱなし」でOK。常に満充電の状態を安全に維持します。 |
「オプティメイト7セレクト」は、アイドリングストップ車用の高性能バッテリーにも対応しています。また、ただ充電するだけでなく、バッテリーの性能を引き出す機能が充実しています。
そのため、充電器を初めて使う方から、より高性能な一台を求める方まで、幅広くおすすめできる製品といえるでしょう。
ダイハツタントのバッテリー上がりは「充電器」による予防が鍵
タントのバッテリー上がりは、日々の少しの注意とメンテナンスで防ぐことができます。その最も確実な方法の一つが、高性能なバッテリー充電器の活用です。
バッテリー上がりを一度経験すると、バッテリー自体の性能が落ちてしまうことも少なくありません。特に「ちょい乗り」が多い方や、週末しか運転しない方は、走行中の充電だけでは不足しがちです。
こうした充電不足を根本から解消し、バッテリーを常にベストな状態に保つために、「オプティメイト7セレクト」のような全自動バッテリー充電器が役立ちます。
オプティメイト7セレクトは、タントのバッテリー状態を自動で診断してくれるのが特徴です。ただ充電するだけでなく、弱ったバッテリーを回復させる機能も備えています。
タントのアイドリングストップ車用バッテリにも対応しており、つなぎっぱなしで安全にメンテナンスを任せられます。
バッテリー上がりの不安を解消したい方は、ぜひオプティメイト7セレクトをご検討ください。